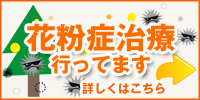こんにちは。げんきや接骨院白井駅前です。
今回はスポーツ障害の「応急処置」について書いていきたいと思います。
【応急手当における概念及び具体的方法】
四肢外傷の王有手当は長年にわたり安静(Rest),冷却(Ice),圧迫(Conpres-sion),挙上(Elevation)の頭文字をとったRICEが基本であると考えられてきたが、近年RICEだけでは損傷した組織の保護が不十分であるとの報告が散見され、RICEに保護(Protection)を加えたPRICEを提唱したのち、必要以上の固定、安静期間はむしろ悪影響を及ぼすとし、安静(Rest)を適度な負荷(Optimal Loading)に変えたPOLICEという概念を提唱しました。POLICEは受傷直後の急性期というよりも、むしろ組織治癒過程の後半フェーズを含めた概念であり”応急処置”すなわち”初期対応”という範囲からはやや拡大されたものであったので、急性期処置(PEACE)と亜急性期管理(LOVE)に分けたPEACE &LOVEという概念を報告しました。
PEACEでは是非の議論が絶えないアイシングが省かれ、抗炎症薬の使用を避けることと教育が追加され、LOVEでは亜急性期の南部組織に対する処置として、負荷(Loading)、オプティミズム(Optimism)、局所への循環促進(Vascularisation)、運動(Exercise)が必要であると述べられました。つまり、RICE,PORICE,PEACEは組織修復過程における急性期管理に重点が置かれたもので、POLICEやLOVEは亜急性期や回復期を含めた概念であると整理できます。
【具体的な処置】
a.安静(Rest),保護(Protection)
安静及び保護は、損傷組織の過度な炎症惹起や腫脹の防止に加え、組織の再損傷を防ぐことを目的とする。POLICEで唱えられている適度な負荷は、”必要以上の安静期間”が循環停滞の遷延化を生じることに警鐘を鳴らすことが意図であり、決して急性期の安静・保護を否定するものではないということを理解すべきです。また、安静及び保護を解除するタイミングについては明確な医学的根拠を示した報告はなく、ここの病態を理解し、疼痛・腫脹・熱感などの注意深い観察から判断することが重要です。
b.アイシング(Icing)
アイシングは、疼痛の緩和、過度な出血の防止、以上な筋収縮の防止を目的とすると、古くから考えられてきました。近年その是非について様々な議論が繰り広げられている背景には、システマチックレビューにおいて遷延化を誘発する可能性があることなどが挙げられる。しかしいずれの報告においても、アイシングの有用性を証明できなかったという結論に留まっているのみであり、アイシングという行為そのものを否定しうる根拠には至っていない。現時点においては”意味がない”と結論づけるべきではないと考え、より詳細な条件下での検討が望まれる。
c.圧迫(Compression)
圧迫は、損傷組織からの過度な出血の防止に加え、腫脹や浮腫の軽減が目的とされ、テーピングまたは包帯を使用した物理的圧迫により腫脹や浮腫を防ぐことで、損傷組織における循環の改善や住むずな炎症の鎮静化、疼痛緩和などが得られ、より早期から運動プログラムの導入が可能になるが報告されています。
d.挙上(Elevation)
挙上は、圧迫同様、損傷組織の腫脹及び浮腫の軽減が目的で、四肢を心臓より高く持ち上げることで、腫脹に伴い停滞した間質液の流れを促進させると考えられているが、その効果を支持する医学的なエビデンスは低く、しかしながら、その簡便さとリスクの低さから現時点では推奨されています。
e.抗炎症薬の使用を避けること
炎症は組織修復過程において必要不可欠であり、受傷直後の抗炎症薬の使用は、むしろ正常な炎症惹起、治癒過程を妨げる可能性が懸念されていることから避けるべきであるという意見があり、一方、スポーツ現場において、痛みを訴えている選手に対して疼痛管理をしないという選択肢はあまりに非現実的であり、さらに疼痛の遷延は神経伝達物質(セロトニンやノルアドレナリン)の低下による疼痛抑制機構の破綻をきたすことも報告されています。あくまで疼痛コントロールを目的とした消炎鎮痛薬の使用までをも、制限する必要があるかは疑問であり、いずれにせよ、日本において無診療投薬は法律上禁じられており、消炎鎮痛薬の使用は医師の判断に委ねるべきです。
f.教育(Education)
電気療法、徒手療法、鍼治療などの受動的な治療は、痛みや機能回復に対して有効性が示されなかったという報告や、むしろ長期的には依存心を生み出し逆効果となることという報告もあっがており、様々な”ハイテク治療オプション”や”魔法の治療”を推奨するのではなく、選手に現実的な目標設定をさせるべきであることを強く推奨している。筆者らもこの点については強く同意しており、過保護が選手やチームの成長を妨げているケースを幾度となく目の当たりにしてきた。自身の身体に起きている病態や重症度を理解させ、次に何を行うべきか自ら考えさせることこそが、現場のアスレティックトレーナーの最も重要な任務の一つであり、選手を成長させることであると考えます。
g.負荷(Loading)
早期の最適な負荷は、物理的刺激に対する細胞応答による組織修復に関与する重要なタンパク質の生成を促進させ、損傷組織の増殖及びリモデリングを促進させると考えられています。
しかし、”最適な負荷”の定義は曖昧であり、開始時期や負荷量の判断を誤ると炎症の再燃や遷延化、組織の再損傷をきたすことも懸念されており、日々の注意深い観察と共に柔軟にアプローチしていくことが重要です。
h.オプティミズム(Optimism)
オプティミズムを日本語訳すると楽観的や楽観主義となるが、メンタルヘルスと捉えていいです。近年、怪我を負ったアスリートに対するメンタルヘルスに関する研究報告が散見され、不安や焦り、落ち込みなど、心理的コンディション不良や悲観的な心理状態が、怪我の回復遅延に関連することが報告されています。心理的要因が組織修復過程、復帰までの期間、復帰時パフォーマンスへも大きな影響を及ぼす可能性が示唆されていることから、受傷長くごに選手と接することの多いアスレティックトレーナーにとって、化学的なエビデンスに基づいたメンタルヘルスケアは、今後重要な役割の一つとして注目されるでしょう。
i.局所への循環促進(Vascularisotion)
いわゆる患部外トレーニングによる心肺機能の維持であり、早期の有酸素運動開始は、損傷組織への循環の改善にとどまらず、運動意欲の獲得にもつながると考えられています。
j.運動(Exercise)
早期運動介入が、足関節捻挫における可動域・筋力・固有知覚・活動性などの早期回復に有用であり、さらには再発率も減少させることが示唆されています。しかし、早期運動介入を推奨する報告において、重度の靱帯損傷や複合靭帯損傷、骨傷を伴うような重症度の高い症例は除外されていることも理解しなければなりません。
また、慢性足関節不安定症(CAI)の予防に外固定が有用であるという報告もあり、早期運動介入が足関節機能回復及び再発予防に一定の効果を与えることは高いエビデンスレベルで確立されているが、開始時期や運動様式の決定には、病態や重症度を考慮した細心の注意が必要です。
参考文献”臨床スポーツ医学Vol 37 No.9”
↓ご相談等ありましたらお気軽にご連絡ください♩↓
↓インスタもやってます♬↓
↓お近くのげんきやグループはこちらから検索♫↓